近年、日本国内でも多くのスタジアムが建設され、大きな話題となっています。
しかしながら反対に、スタジアムの建設が上手くいっていないケースも多く、その理由として、主に税金を使うか否かといった点についての議論が焦点です。
個人的には、税金に頼ることなくスタジアムを建設していければいいと思っています。・・・まあ、この話を始めると止まらないので、いったんこのあたりで、また別の機会に書きましょう。
話を戻して、結局のところ、スタジアムを建設したとしても、その維持管理費や人件費など、コストがかさみ赤字になるケースが多いことが、どのチームも一歩を踏み出せない要因でしょう。
というわけで今回は、収益を上げる方法、スタジアムの運営方法についてフォーカスしていきたいと思います。
トピックとしては、私のいるイギリス、ロンドンとその周辺の4つのスタジアム(エミレーツスタジアム、ウェンブリースタジアム、トッテナム・ホットスパースタジアム、Meadow Park)を例にしてご紹介していきたいと思います。
その4つのスタジアムそれぞれが、違った特徴があり維持管理をしているスタジアムですので、これを参考にスタジアムの運営方法を模索していっていただければと思います(日本とは規模が違うという点はここでは無し)。
このブログの作者Ikumiはアーセナルで
ブログの作者Ikumi
グラウンズパーソン(グラウンドキーパー)として働いています。
今までも芝生に関しての記事をたくさん書いてきましたので、
気になる方々はぜひ過去の記事を遡ってみてください。
SNSも発信中。気になる方はぜひフォローを!
Twitter: @Ikumi_grounds
イングランドにおけるトップレベルのスタジアム運営の前提
イングランドにおけるスタジアムの運営としては、基本的に多くのクラブがスタジアムツアーを毎日行い、そして併設されているクラブストアでクラブのオフィシャルグッズを販売しています。
そして個人的にすごいと感じる点としては、試合の日にVIPが使用できる部屋をかなり高額で用意している点。
エミレーツスタジアムを例に挙げると企業のボックスシートが2,222席ほど用意されているそうですが、その座席における収益だけで、エミレーツスタジアム以前のアーセナルの本拠地だったハイバリースタジアム全体の収益とほとんど変わらないそうです。
実は私も以前、あるプレミアリーグスタジアムの企業ボックスシートに招待されたことがありまして、試合の日に訪問させていただきましたが、そこでは常に料理は提供され続け、飲み物はなんでも飲み放題、バーテンダー付き、シートはヒーター付き、トイレは混雑しないなど、素晴らしいホスピタリティを受けました。
日本のスタジアムも、こういったVIP用の席をもう少し確保して販売できたら、面白いのではないかと思います。
それではここからは、各スタジアムについてみていきましょう。
エミレーツスタジアム:男子女子両チームでキャパシティ最大限活用
アーセナルのホームスタジアムであるエミレーツスタジアム。今回はスタジアムの詳しい紹介は省きます。

プレミアリーグの人気が凄まじいのは多くの方々が認知していることでしょう。チケットが取れない問題は有名な話で、アーセナルも同様。
一方で女子チームはというと、近年一気にその人気を爆発させています。
24-25シーズンにおける女子プレミアリーグにおける観客が多かった試合では、なんとトップ5すべてがアーセナルのホームゲーム。平均観客動員数も、アーセナルが1位で28808人と、2位のチェルシー9426人の約3倍も多く動員しています。
そして25-26シーズンから全てのリーグ戦をエミレーツスタジアムで行うことが決定しました。
このように、クラブチームの人気が凄まじいことで、スタジアムの稼働率を上げ、そして稼働率を上げるだけではなく、客席も最大限に活用することで、スタジアムの運営しています。
アーセナルのケースでは、プロフェッショナルクラブとして、スタジアムを利用する団体すべての人気を上げて最大限活用するといった例でした。
とはいえ、これができれば、どこのクラブもスタジアム建設には苦戦しないでしょう。
次は特定のクラブがいるわけではないスタジアムを紹介します。
ウェンブリースタジアム:試合ない日の合間にコンサートやその他イベントを行う
続いてはイングランド最大のキャパシティを誇るウェンブリースタジアム。

私も2024年10月から仕事させていただいていて、まもなく1年が迎えようとしています。
この1年間、ウェンブリースタジアムで仕事をしてみての感想として、なかなか数のコンサートを行っている点に驚きました。
それもそのはず。ウェンブリースタジアムはサッカーの聖地として知られていますが、サッカーで利用する場面としては、男子女子イングランド代表のホームゲーム(たまに別会場で行われる場合アリ)、カラバオカップ決勝、FAカップ準決勝2試合と決勝、各カテゴリーの昇格プレーオフ3試合、そしてコミュニティシールド1試合、たまに順番が来たらUEFAチャンピオンズリーグファイナル。意外と少ないのです。
そのため近年では、NFLを誘致してイングランド国内でゲームを行っています。
ただ、それでもやはり多くはありません。確かにこの1年ウェンブリースタジアムのマッチデースタッフとして参加し、どのゲームもほぼ満席といった状態を見てきましたが、これだけでは赤字運営でしょう。
それを解消するために、ウェンブリースタジアムでは、シーズンオフの期間やサッカーがない日に思いっきりコンサートを行います。もちろん他のスタジアム、エミレーツスタジアムでもオフシーズンにはコンサートを行っていました。
しかしウェンブリースタジアムは、一味違います。
2025年は8月10日にコミュニティシールドを行いましたが、実はその1週間前までオアシスのコンサートが行われていたという非常にタイトなスケジュールでした。
2日間で芝生を撤去して、2日間で芝生を張り、そして2日間で芝刈やライン引きを行い試合の準備。そしてコミュニティシールドを迎えました。
ですが驚くのはまだ早いです。
このコミュニティシールドを行ったすぐあとから、今度はブラックピンクのコンサートの準備が行われ、次のイングランド代表のゲームがある10月上旬までコンサートなどで最大限活用するとのこと。
そしてイングランド代表のゲームがある1週間前に再び芝生の撤去と芝張りを行い、男子イングランド代表がゲームをするというわけです。
ウェンブリースタジアムの例では、9万人というキャパシティを最大限活用する例と言えます。サッカーだけでは赤字になってしまう点を、いかにして他で補填するのか。
通常、コンサートを行えば芝生にダメージが入るのは当たり前です。しかしウェンブリースタジアムの場合は、コンサートを行ったとしても、圃場で育てた芝生を持ってきて張ることで、短いスパンでコンサートとサッカーを切り替えられる術を手に入れました。
それで芝生が持つのか?という声が出そうですが、少なくとも先日のコミュニティシールドでは、私もピッチ上にいましたが、剥がれることもなく特に問題ありませんでした。芝生が張り替えたばかりというのを、観戦していた段階で気が付いた方がどれくらいいらっしゃるのか気になりますね。
この運営方法は、日本国内でも真似できるような気もします。日本でもすでに張り替えてスタジアムの運営しているところもあるそうですが、ハイブリッドターフがあるかないかは大きいかもしれません。
ウェンブリースタジアムの場合は、カーペットタイプのハイブリッドターフを採用し、芝生は寒地型、圃場から切り取る芝生の厚さも約8cmほど切り取って持ってきているので、なかなかこれを真似するのは大変かもしれません。

キャパシティの大きなスタジアム、コンサートの需要が大きいスタジアムであれば、これは1つのロールモデルになりそう。そう思わせてくれたため、今回紹介させていただきました。
トッテナム・ホットスパースタジアム:天然芝と人工芝の二刀流
3つ目はトッテナム・ホットスパースタジアム。名前の通りトッテナム・ホットスパーが使用するスタジアムです。

オープンから約6年が経過したため、多くの人がトッテナム・ホットスパースタジアムの構造について耳にしている方が増えてきているでしょうが、簡単に紹介しますと、天然芝と人工芝のどちらも一緒に同じ場所に所有している極めてまれなスタジアムです。
詳しい紹介は以前ブログに書いていますので、そちらをご覧ください。

このスタジアムの何がすごいのかというと、天然芝と人工芝を入れ替えることができる点。正確に言えば、天然芝を三分割して駐車場に格納することが可能で、そして元あった場所には人工芝があるという形です。
「天然芝格納して大丈夫?」といった声が聞こえてきそうですが、こちらはグローライトをはじめ、全自動芝刈りロボや散水設備など、地下であっても設備が充実しているので、数日間であれば問題ないとのこと。
この方式にすることで、例えシーズン中であってもコンサートや芝生にダメージが入る大きなイベントを行える点が素晴らしいポイント。
サッカークラブのスタジアムである以上、サッカー選手がいかにケガしないか、この辺りが最も大事になります。
そのため、シーズン中に芝生の上でコンサートを行うのは、基本的にNG(クラブの持ち物だからです。クラブの持ち物ではない日本のスタジアムは仕方ないです)。
とはいえサッカーの試合数もそこまで多くない中で、いかに収益をあげるのか。トッテナム・ホットスパースタジアムの場合は、切り替えることで、人工芝の上でコンサートを行えば問題ないとしています。
また、NFLも行いますし、他にもイベントは人工芝で行うことで、スタジアムを最大限活用できます。
それ以外にも、スタジアムの中にはカートレース場があったり、スタジアムの屋根に上るアクティビティがあったり、スタジアムの中を一種のアトラクションに変えて多種多様に活用しています。
といったところで、この天然芝の構造、どう生育しているのか、そして格納するのはいつなのか、本当に地下でも大丈夫なのか。気になってきますね。
このトッテナム・ホットスパースタジアムのケースのように、さすがに二刀流で運営するというのは厳しいでしょうが、様々なアクティビティを併設することでファンを獲得するという点でいえば、長崎スタジアムシティなどは、その例に当てはまるのではないかと思います。スタジアム上空を飛べるジップラインもありますからね。
日本で運営するのであれば、現実問題としていかにスタジアム周辺を活性化させて全体で盛り上げるのか、このあたりがトッテナム・ホットスパースタジアムからは学べるのではないでしょうか?
ちなみに建設費は、当時の為替レートで、ほぼ日本の国立競技場と同じです。
Meadow Park:ローカルチームを大きなクラブが手助けする
最後はあまりにもローカルすぎて多くの方の頭の中に??が浮かんだことでしょう。
そしてこちらのケースでは、収益を上げる、というよりは、運営方法に注目してほしいという感じです。
このスタジアムは、普段はBorehamwood FCというサッカークラブが使用しているスタジアムですが、時折アーセナルも利用しており、主に女子チームがカップ戦で使用していたり、U-21のホームスタジアムとしての役割も担っています。

そして芝生を管理しているのは果たしてどこなのか?
実はこのスタジアムも、アーセナルFCのグラウンズチームの管理領域で、我々が芝生の管理をしています。
常駐しているのは3人ほどになりますが、マッチデーには私もよくお手伝いに行きます。
4500人ほど収容可能で、立見席がある非常にローカルな古き良きスタジアムとなっています。
とはいえ25-26シーズンに5部リーグに相当するナショナルリーグにようやく昇格したクラブですから、スタジアムの維持管理、特に天然芝であれば、普通なら難しいでしょう。
そうした中で、アーセナルのような大きなクラブが芝生の管理を支援することで、下部リーグのクラブでもスタジアムを天然芝で運営できるシステムを作っています。
この例からは、日本国内でも大きなサッカークラブが下部リーグのクラブチームを手助けできるような仕組みができるようになれば良いのではないか?と個人的には思っています。
もちろん、今の現状ではJ1のクラブチームですら、自分たちのところで精一杯なのが現状ですが、こうしてフットボールの文化を作っていくことが、私は理想だと感じます。
まとめ
現実的に日本国内で取り入れることが出来そうな例は、まずサッカーチームが人気を獲得して、そのキャパシティを最大限活用することが望ましいでしょう。
とはいえ、芝生のダメージを考えると、利用頻度を増やすのが難しいのも事実。
そうした中で、ウェンブリースタジアムのようなコンサートを次々と行い、カーペットタイプのハイブリッドターフを使用することで、すぐに試合を行っても問題ないようなコンディションに仕上げるという例は、非常に魅力的に思います。
多くの方が芝生の管理にはお金がかかるといいますが、よく考えていただきたいのは、選手たちが何人もプレーするその足元の「舞台」に投資をすることは、選手生命を守ることでもあり、選手全員に投資していることでもある、と私は思っています。
この中の「選手」に関しては、サッカーだけでなく、ラグビーや陸上、野球などすべての芝生の上でスポーツを行う「選手」が含まれています。
良い芝生のコンディションを維持することで、ケガを減らし、そしてチームとして最善な選手選考を可能にし、チームの勝利に大きく貢献できるのが「芝生」であると思い、なかなかこの部分を理解していただける方が少ないのは事実ですが、少しずつ芝生の重要性に気が付いていただけるように、今後も発信していきたいと思います。
というわけで今回は、そんな芝生、そしてスタジアムを運営、維持管理するために必要な収益をスタジアムはどのようにして上げていくのか、イングランドを例に見ていこう、そんなお話でした。
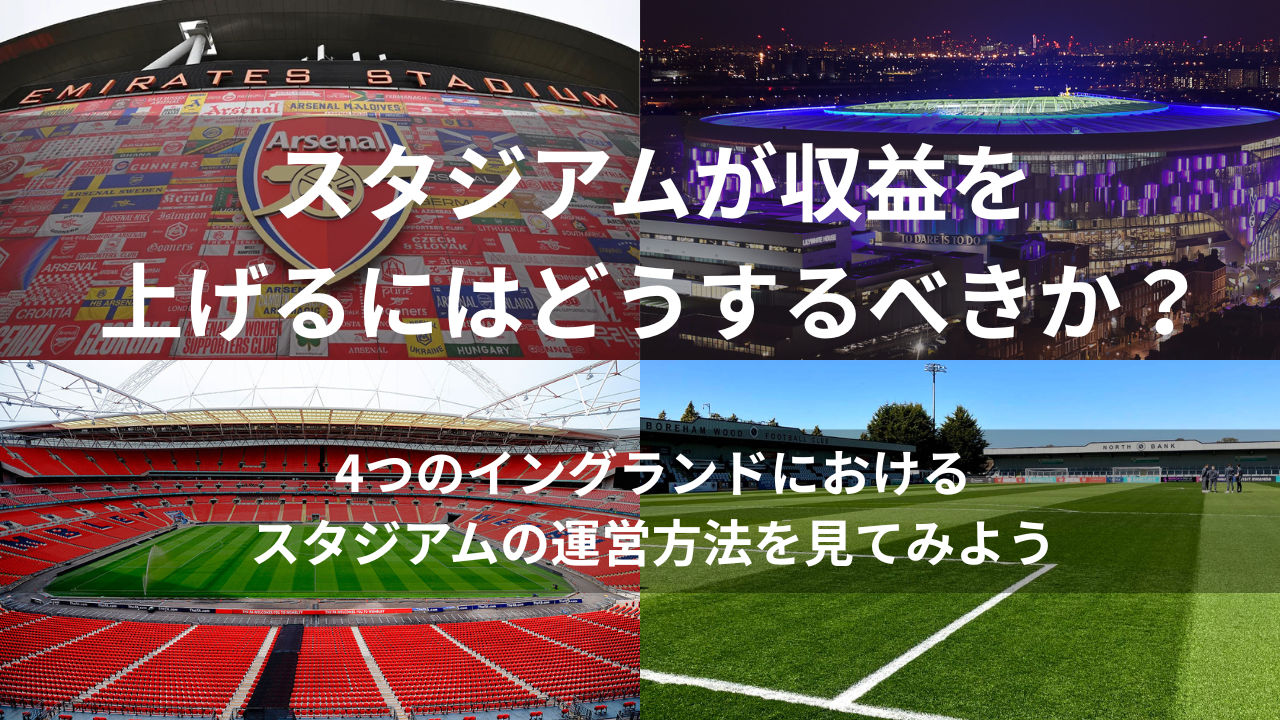


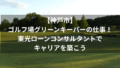
コメント